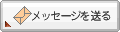2016年04月29日
東ドイツ メダルバー製作
メダルバーやリボンバーをバラの状態から組み立てていく作業を紹介する記事です。

この記事を書こうと思ったのは、既製品や完成品の画像は見たことがあるけど製作方法が解らず
ebayや色々なサイトを独語コピペで片っ端から見て回ったり国内東独マニアの流れてしまったツイートを集めたりと
メダルバーを作るためだけに結構時間を喰ってしまったので100%正しく効率的かはさて置き、やり方の1つとして「日本語版がネットに埋もれない形であってもいいかなー」っていう気持ちから始ったわけでして・・・
この記事を書こうと思ったのは、既製品や完成品の画像は見たことがあるけど製作方法が解らず
ebayや色々なサイトを独語コピペで片っ端から見て回ったり国内東独マニアの流れてしまったツイートを集めたりと
メダルバーを作るためだけに結構時間を喰ってしまったので100%正しく効率的かはさて置き、やり方の1つとして「日本語版がネットに埋もれない形であってもいいかなー」っていう気持ちから始ったわけでして・・・
メダル以外に用意するものは
●ラジオペンチ
●マイナスドライバー
●適当な紙
●略綬受け金具
●メダルバー用板
●失敗しても人のせいにしない優秀労働者な心構え
以上が存在している(最後は冗談ですが)前提で手順進めて行きたいと思います。
金具・板

画像の金具、略綬受け金具とメダルバー用板(等間隔に穴の空いたやつ)というのは文章化する上で造語しました。
受け金具は裏に取り付け用針の有無、板と受け金具の連数を間違わないよう調達してください。
画像の金具は4連用です。メダル1つの取り付けに板の穴は2つ消費されます。
針の取り外し
まず取り付けたいメダルをひっくり返して針のついた金具を外す作業をします。

金具は尖がった金属を曲げて抜け留めにしているだけなので →← こんな感じで金具を抑えてある所を起してあげます。
+Achtung!+
起した部分は再使用するので丁寧に行いましょう!!

曲げの具合にも寄りますがマイナスドライバーを隙間に入れてある程度起すと楽です。
ラジオペンチなんかも使って金具が取れるくらいになったらOKです。
板&金具への取り付け
今度は先ほどと逆手順で板の穴に入れて尖った部分を曲げて、板を受け金具にスライドして入れてあげれば大体完成・・・

なんですが・・・
自分はここで重大なミスを犯しました!!
板にメダルを密着させて留めた状態で受け金具に板を差し込むと
受け金具の赤くぬった部分が差し込むたびにメダルのリボンを傷つけながら進んでいったり
「よれて」差し込めなくなったりしました・・・。(画像参照

これじゃぁ華々しいメダルにとっても良くないので自分なりに工夫をして引っかからないような方法を考えてみました。

先ほどの赤く塗った部分の厚さか少し薄いくらいに要らない紙を折って例の曲げる部分に差し込んでやります。
こうすることで板とメダルの間に隙間が出来てリボンへの損傷が防がれる!!というわけです!
仕上げ留め
上手く板を差し込むことが出来たら最後は板が抜けないよう両端の金具を起しましょう。

受け金具は個体差ありまくりで、この個体だと画像のようにしっかりと根元から曲げても板への掛かりが浅いくらいです。
この部分曲げたり戻したりと弄ってるとポキンと折れてしまうのでなるべく一発で決めてあげましょう!
コレにて完成あとは服に取り付けてあげましょう。
材質や形状の理由で後戻りを繰り返すと使い物にならない部位が有るのでしつこいようですが作業を実行する前にメダルの並びや板との隙間を良く確認しましょう!!
●ラジオペンチ
●マイナスドライバー
●適当な紙
●略綬受け金具
●メダルバー用板
●失敗しても人のせいにしない優秀労働者な心構え
以上が存在している(最後は冗談ですが)前提で手順進めて行きたいと思います。
金具・板
画像の金具、略綬受け金具とメダルバー用板(等間隔に穴の空いたやつ)というのは文章化する上で造語しました。
受け金具は裏に取り付け用針の有無、板と受け金具の連数を間違わないよう調達してください。
画像の金具は4連用です。メダル1つの取り付けに板の穴は2つ消費されます。
針の取り外し
まず取り付けたいメダルをひっくり返して針のついた金具を外す作業をします。
金具は尖がった金属を曲げて抜け留めにしているだけなので →← こんな感じで金具を抑えてある所を起してあげます。
+Achtung!+
起した部分は再使用するので丁寧に行いましょう!!
曲げの具合にも寄りますがマイナスドライバーを隙間に入れてある程度起すと楽です。
ラジオペンチなんかも使って金具が取れるくらいになったらOKです。
板&金具への取り付け
今度は先ほどと逆手順で板の穴に入れて尖った部分を曲げて、板を受け金具にスライドして入れてあげれば大体完成・・・
なんですが・・・
自分はここで重大なミスを犯しました!!
板にメダルを密着させて留めた状態で受け金具に板を差し込むと
受け金具の赤くぬった部分が差し込むたびにメダルのリボンを傷つけながら進んでいったり
「よれて」差し込めなくなったりしました・・・。(画像参照
これじゃぁ華々しいメダルにとっても良くないので自分なりに工夫をして引っかからないような方法を考えてみました。
先ほどの赤く塗った部分の厚さか少し薄いくらいに要らない紙を折って例の曲げる部分に差し込んでやります。
こうすることで板とメダルの間に隙間が出来てリボンへの損傷が防がれる!!というわけです!
仕上げ留め
上手く板を差し込むことが出来たら最後は板が抜けないよう両端の金具を起しましょう。
受け金具は個体差ありまくりで、この個体だと画像のようにしっかりと根元から曲げても板への掛かりが浅いくらいです。
この部分曲げたり戻したりと弄ってるとポキンと折れてしまうのでなるべく一発で決めてあげましょう!
コレにて完成あとは服に取り付けてあげましょう。
材質や形状の理由で後戻りを繰り返すと使い物にならない部位が有るのでしつこいようですが作業を実行する前にメダルの並びや板との隙間を良く確認しましょう!!
Posted by kabuzako at 13:50│Comments(2)
│バッチ・略綬関係
この記事へのコメント
お久しぶりです。
しばらくNVAは整理にかこつけてお休みしていたのですが、同記事のようにメダルバーを調整していたころを懐かしく思い出しました。
VEB 壁の中のジパング様のブログもだいぶ充実されたようで、特に下士官兵の記事は大いに参考になりました。
しばらくNVAは整理にかこつけてお休みしていたのですが、同記事のようにメダルバーを調整していたころを懐かしく思い出しました。
VEB 壁の中のジパング様のブログもだいぶ充実されたようで、特に下士官兵の記事は大いに参考になりました。
Posted by KALEU at 2016年05月03日 01:41
KALEU さん
ブログ、参考にしていました。
実際に着用+徽章パターンの作成というとても調べる・見る側としては勉強になるものでした・・・!(休止中なのが残念です!
>>特に下士官兵の記事は大いに参考
ありがとうございます。
模索の途中経過を記したような内容ですが
参考になったと言われると、下士官をほんのり意識して専攻してた自分はとてもに嬉しいです。
今後ともよろしくお願いします。
ブログ、参考にしていました。
実際に着用+徽章パターンの作成というとても調べる・見る側としては勉強になるものでした・・・!(休止中なのが残念です!
>>特に下士官兵の記事は大いに参考
ありがとうございます。
模索の途中経過を記したような内容ですが
参考になったと言われると、下士官をほんのり意識して専攻してた自分はとてもに嬉しいです。
今後ともよろしくお願いします。
Posted by kabuzako at 2016年05月07日 20:10
at 2016年05月07日 20:10
 at 2016年05月07日 20:10
at 2016年05月07日 20:10※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。